「日本の平均貯蓄額は〇〇円」というニュースを見て、「みんな、こんなに持っているの?」と驚いたことはありませんか?
実は、その数字、あなたの感覚の方が正しいかもしれません。
毎年発表される「家計の金融行動調査」は、日本の家計のリアルな姿を知るための貴重なデータです。しかし、この調査結果をそのまま鵜呑みにすると、思わぬ誤解を招くことがあります。
この記事では、「平均値」のカラクリから、本当に見るべきデータ、そしてあなた自身の家計管理にどう活かすかまで、専門家やメディアが語らない調査の裏側を徹底解説します。
1. 「平均値」は富裕層が引き上げている!金融資産の”本当の格差”
まず、最大の落とし穴が「平均値」です。
**「平均値」**は、調査対象者全員の貯蓄額を合計し、人数で割ったものです。
一方、**「中央値」**は、金額の低い順に並べたときに、ちょうど真ん中にくる値です。
例えば、10人のグループで、9人が100万円、1人が1億円の貯蓄を持っていたとします。
- 平均値:(100万円 × 9人 + 1億円) ÷ 10人 = 1,090万円
- 中央値:10人中、5番目と6番目の人の値なので100万円
どうでしょうか?平均値は「約1,090万円」と算出されますが、これはグループのほとんどの人にとって、全く現実離れした数字です。
家計の金融行動調査でも同じことが起きています。ごく一部の富裕層が多額の資産を保有しているため、平均値がぐっと引き上げられているのです。
もしあなたが「平均貯蓄額」を見て焦りを感じているなら、まず見るべきは**「中央値」**です。中央値は、より多くの一般家庭の実態を反映しています。
2. 回答の偏り:”本音”を言えない私たち
次に、データの信頼性に関わる根本的な問題があります。それは、調査への回答率の低さと、回答者の正直さです。
【正直に答えますか?】
もし、あなたのもとに「年収と全資産を教えてください」という調査票が届いたら、どうしますか?
多くの方が、プライバシー保護の観点から回答をためらったり、協力を拒否したりするのではないでしょうか。さらに、仮に答えたとしても、正確な数字を申告することには大きな抵抗があるはずです。
「だいたいの金額を少し少なめに書くか…」
「面倒だから、貯蓄はゼロって書いておこう…」
このような心理はごく自然なことです。特に、多額の金融資産を持つ人ほど、詳細な情報を明かすことに強い抵抗を感じます。
ちなみに私なら、回答しないか、なんとなく適当な(実際より低めに)回答しちゃいますね!
この心理的なハードルが、調査結果に大きな偏りをもたらします。
- 高所得者や富裕層が調査から抜け落ちやすいため、全体のデータが過小評価される可能性があります。
- 回答した人でも、資産を過小申告する傾向が強いため、申告された金額が実際の資産額よりも少ないケースが頻繁に発生します。
つまり、家計の金融行動調査の結果は、**「回答してくれた人たちの平均的な姿」**であり、日本全体の家計の姿を完璧に反映しているわけではないのです。
3. データに惑わされない!本当に見るべきポイント
では、家計の金融行動調査は全く当てにならないのでしょうか?
決してそんなことはありません。見方さえ知っていれば、あなたの家計改善に役立つ貴重な情報源となります。
ポイント1:中央値と階級別データを比較する
「平均値」に一喜一憂するのではなく、「中央値」を自身の立ち位置の参考にしましょう。さらに、金融資産の**「階級別」**データ(例:「金融資産非保有世帯が〇%」「500万円〜1000万円未満の世帯が〇%」)を見ることで、世帯全体の分布を把握できます。
このデータを見れば、多くの人がどれくらいの資産を持っているか、自分がどの層にいるのかが客観的にわかります。
ポイント2:単年度ではなく長期トレンドで見る
単年のデータは、その年の景気や株価の変動に大きく影響されます。しかし、数年分のデータを比較することで、家計が長期的にどう変化しているかのトレンドが見えてきます。
「共働き世帯の貯蓄が増えている」「若い世代のNISA利用が増加している」といった本質的な動向は、長期的なトレンドからこそ読み取れるのです。
ポイント3:他調査と比較する
家計に関する公的調査は他にもあります。例えば、総務省の**「家計調査」**は、収入や支出の動向を細かく追跡しています。これらの複数のデータを組み合わせることで、より多角的に日本の家計の実態を捉えることができます。
まとめ:データは”地図”、人生の”羅針盤”ではない
家計の金融行動調査は、あなたの人生の羅針盤ではありません。あくまで、自分の現在地や周囲の状況を知るための**「地図」**に過ぎないのです。
「平均貯蓄額」という数字は、あくまで参考の一つ。自分の家庭のライフプランや目標に照らし合わせて、自分に合ったペースで資産形成を進めていくことが最も重要です。
他人の家計を気にするよりも、今日からできることを一つずつ実行していきましょう。
- 無駄な支出を減らす
- iDeCoやNISAを活用して積立投資を始める
- 副業で収入を増やす
あなたの家計は、あなた自身の行動でしか変わりません。
この調査結果を、あなたの家計を見直すきっかけにしてください。
【この記事のまとめ】
- 「平均値」は富裕層の影響で大きく引き上げられている。
- より多くの世帯の実態を示すのは「中央値」である。
- 調査には回答拒否や過小申告といったバイアスが含まれる。
- データは「地図」として使い、あなたの人生の「羅針盤」は自分で決めるべきである。

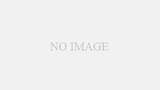
コメント